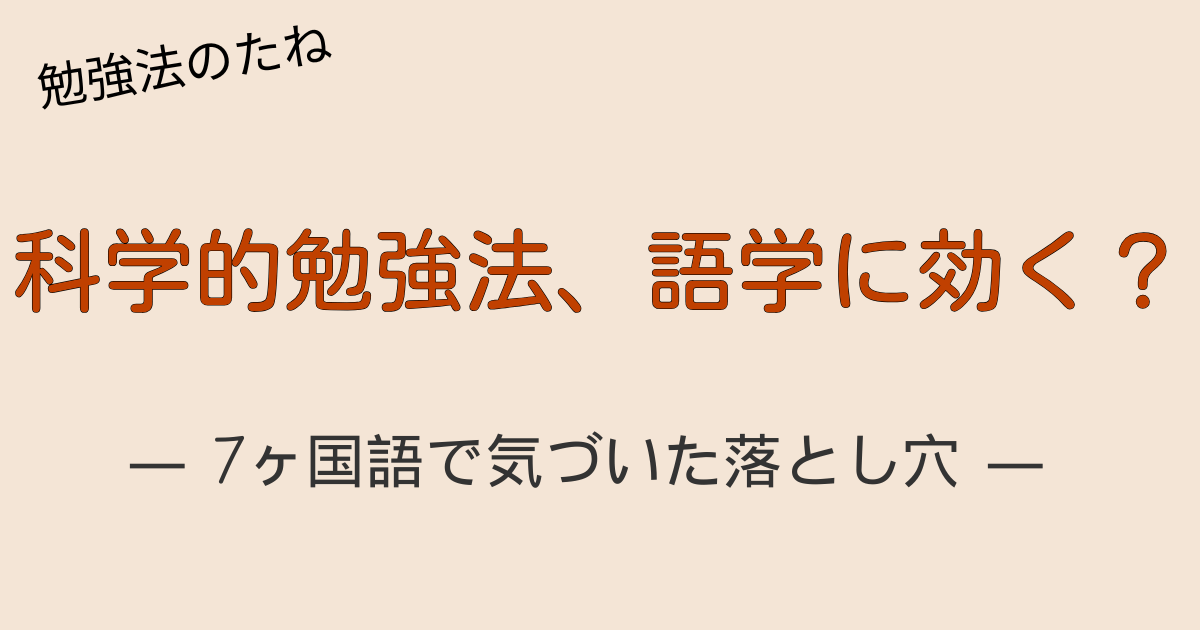「科学的根拠がある勉強法」という言葉よく聞きませんか?
たとえば、
「脳科学に基づく最速の学習法」
「東大生がやっていた記憶術」
「エビングハウスの忘却曲線」など──どれも魅力的なフレーズです。
もちろん、ボクも気になりました。
「これを使えば、もっと効率よく外国語を学べるのでは?」と。
なにしろ、当時のボクは7ヶ国語を学んできた語学好き。
特に第4外国語以降、「科学的なアプローチこそ近道だ」と思い込んでいた時期がありました。
でも、実際にやってみると……そこには大きな落とし穴があったのです。
動画では科学的学習法を試したけど効果がなかった体験を語っています。
「科学的勉強法」は本当に効果があるのか?
長年、「東大式」「ハーバード式」など、
いかにも頭が良くなりそうなネーミングの勉強法がSNSや書籍で話題になっていますね。
ボクがこれらの勉強法を集めていたのは7年前ですから、
少なくとも当時から、こうした勉強法が流行っていたのでしょう。
「脳科学に基づく」とか「記憶の定着率が何%向上」など、
いかにも効果が数値で証明されているような説明もありますよね。
ボク自身も、こうした勉強法に飛びついたひとりです。
中国語と英語がある程度わかったので、
「第4外国語は比較的容易に上達するだろう。
ましてや、科学的勉強法を取り入れれば、
もっと早く、効率的に習得できるはずだ。」と期待していました。
科学的勉強法で語学は上達するのか?
「科学的根拠がある」とされる学習法で、
具体的にいくつか挙げてみると、
・分散学習(インターバル学習)
・アクティブラーニング
・エビングハウスの忘却曲線に基づいた復習
・スペーシング効果を意識した単語暗記 など
一見、どれも合理的で納得できる内容でした。
けれど、実際にこれらで勉強した外国語は——使い物になりませんでした。
確かに、暗記の効率は上がったかもしれません。
語学は「知っている」だけでは使えないんですね。
単語を知っていても、会話になると口から出てこない。
文法を理解していても、実際の会話のスピードにはついていけない。
つまり、「知識」と「運用」はまったく別物だったのです。
効果があったのは「使う」ことに集中した学習法
7ヶ国語勉強して、中国語だけ伸びて、通訳になったわけですが、
中国語は「科学的勉強法」をやったわけではありませんでした。
何をやったかというと
・ネイティブとスマホでチャット
・映画を観まくる
これだけで、日常会話はできるようになりました。
ネイティブとの会話の回数が増えるにつれて、
語彙も増えていき、さらに聞き取れるようになっていきました。
アウトプット中心で、暗記はしなかったです。
特にチャットでのやり取りは、即時フィードバックが得られ、
自然と表現も増えていきましたね。
「でも、これじゃ試験は合格できないんじゃないの?」
こう思うかもですが、
HSK6級には8割以上得点して合格しました。

結論:語学は暗記でなく、「使ってなんぼ」
科学的勉強法は、暗記をして、
単語テストなどをするには、一時的に効果があるかもしれません。
しかし、ボク自身の体験では、それで使えるようにはなりませんでした。
数年経った今では、当時覚えた単語はほぼ何も思い出せません。
語学は、生きた言葉です。
暗記ではなく、使いながら覚える・試しながら磨く、そんなプロセスが欠かせません。
もちろん、科学的勉強法を完全に否定するわけではありません。
ただ、語学に関しては「科学的=即効性がある」と過信せず、
自分で体験しながら最適な方法を見つけていくことが大切だと、
7ヶ国語を学んだ今、強く実感しています。
※この記事の内容をさらに深掘りしたnoteを現在執筆中です。
公開されたらリンクをここに追加します。