中国語を勉強したいけど、どこから始めればいいか分からない。
中級から抜け出せない、HSK6級を取得しても会話ができない、独学で中国語を習得したい、使える中国語を身につけたい…。
そんなあなたにぴったりな発音や文法の学習法、効率的な勉強法を解説します。
ボク自身、高卒からプロ通訳として中国に移住し、奥さんも中国人という立場から、実際に試した学習法をもとに、このロードマップを作成しました。失敗も経験し、それを反映させた内容です。
学習の進め方を変えるタイミングに来たあなた、この記事を参考にして、中国語学習を進めてください!
1.学習の準備
学習を始める前に最も重要なのは、基礎をしっかりと固めることです。中国語の発音は、日本語とは大きく異なるため、最初にしっかりとした発音を習得することが、後の学習をスムーズに進めるカギとなります。
このセクションでは、発音の基礎からピンインの正しい使い方まで、学習を始めるために必要な準備を整えます。まずは発音をしっかりと理解し、耳と口を慣れさせていきましょう。
以下のように最適化してみました。
ロードマップの全体の流れ
まず、発音とピンインのルールを軽く確認したら、タイピング練習や中国語の映画、ドラマなどに触れ、実践しながら覚えていきます。「覚えてから実践」ではなく「実践しながら覚える」のが鉄則です。その後、HSK1級の文法レッスンを一つずつ進めていき、シャドーイングを中心に繰り返し練習します。例文をタイピングすることでピンインも復習できます。多聴とスピーキングを中心に進め、ある程度のレベルに達したら多読を取り入れます。
HSK3級まで続けると、日常会話もできるようになり、中国語脳が育って語彙が自然と増えます。その段階で多読を取り入れ、SNSなどでたくさんの文章を読んで語感を養います。試験を受けない場合は、HSK4級以降は確認程度でOKです。ボクも参考書なしでHSK6級に合格しました。この方法をさらに進化させた形で紹介します。
発音(四声)とピンインの基礎
中国語の発音の基礎は「四声」と「ピンイン」の習得から始まります。四声は音の高さを表し、意味に影響を与えるため、正確にマスターすることが大切です。ピンインは発音をアルファベットで表す方法で、学習初期には欠かせません。
発音練習では「完璧を目指さない」ことがポイントです。中国には方言が多く、標準語ですらアクセントがあります。ネイティブと同じ発音を目指すのではなく、音を聞き取れるレベルを目標にしましょう。発音がある程度できるようになれば、ネイティブの音が自然と聞き取れるようになります。
音のリズムと流れ
中国語は音のリズムと流れが非常に重要です。日本語のように一定のリズムではなく、声の上がり下がりが頻繁に変化します。このリズムを習得することで、言葉が自然に聞こえるようになります。最初はゆっくりと、リズムに合わせた練習を積み重ねることが大切です。
ここまでの基礎を押さえたら、次に実践的な練習を取り入れていきましょう。おすすめの発音練習方法やリズムを身につけるトレーニングを以下の記事で紹介しています。詳しくはこちらをご覧ください。
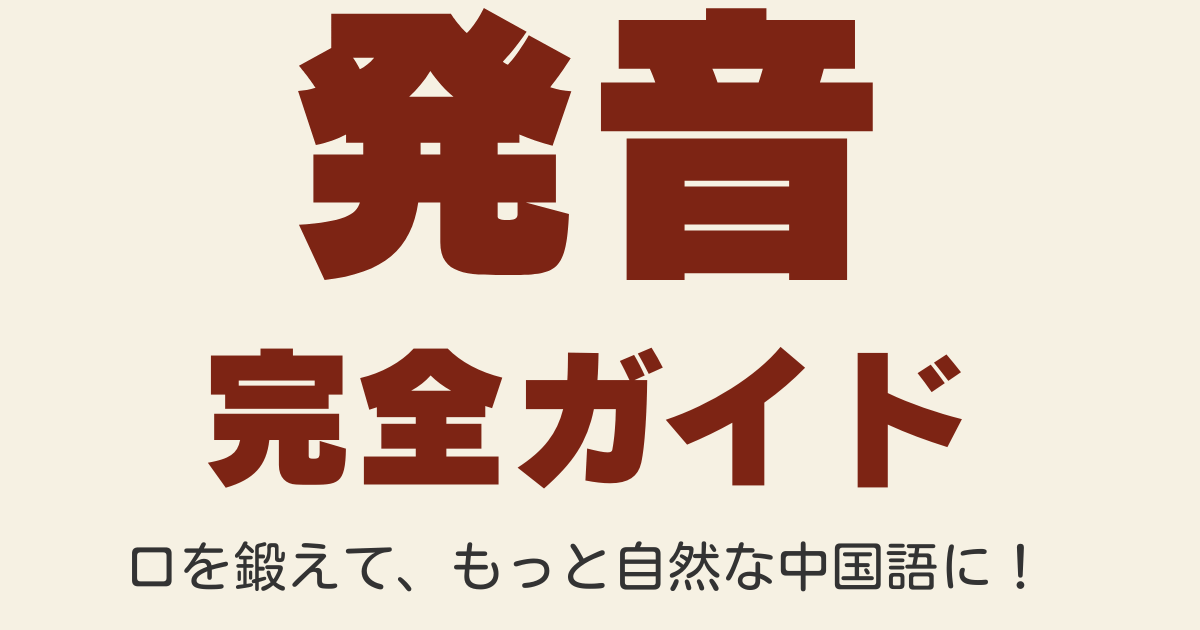
タイピング練習(ピンイン入力)
中国語を学ぶ上で、ピンインのタイピング練習は非常に有効です。ピンインは発音をアルファベットで表現したものなので、タイピングを通じて単語やフレーズの構成を体験することができます。
ピンイン入力を練習することで、書くスピードが上がり、同時に発音も意識できます。特に、ネイティブとのチャットや実際のコミュニケーションに役立つスキルです。
タイピング練習は、単なる入力作業ではなく、中国語を実際に使う感覚を養うための重要なスキルです。ボクは入門レベルからピンイン入力を練習していたので、ピンインの習得がスムーズに進みました。タイピングを通じて、発音や単語の構成を意識しながら学ぶことができ、実際の会話やネイティブとのチャットに役立ちます。
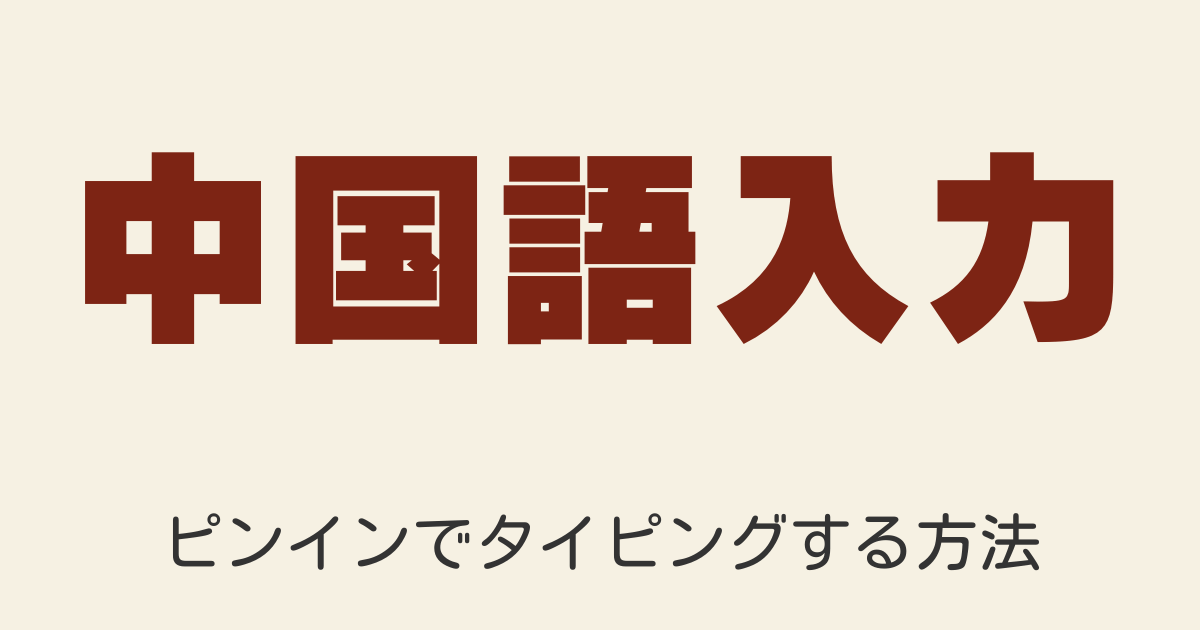
2. HSK1級 – 基礎を固める
HSK1級は中国語学習の基礎を固めるための重要なステップです。この段階では、基本の文法や単語をしっかり身につけることが目標です。単語も単語帳などで暗記するのではなく、文章に触れながら覚えます。「覚えてから使う」ではなく「実践しながら覚える」が鉄則でしたね。
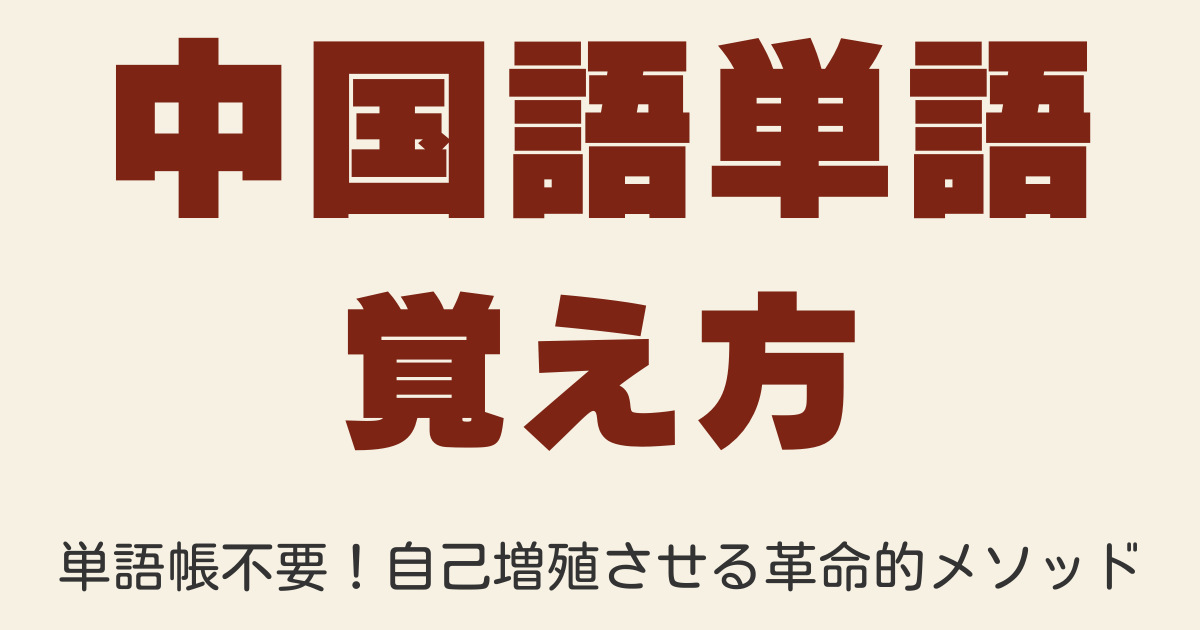
同時に、発音やリズムを意識しながら、シャドーイングやリスニング練習を取り入れることで、聞き取り力と発話力を鍛えましょう。また、タイピングでピンイン入力に慣れることで、後のチャットや作文に役立ちます。
2.1 基本の文法と単語
HSK1級では、まず基本的な文法と単語を習得することが大切です。文法の基礎としては、「主語+動詞+目的語」の語順や「是(shì)構文」「有(yǒu)構文」などを理解しましょう。単語は日常会話で使う基本単語を中心に覚え、発音とセットで学ぶと効果的です。
また以下の文法レッスンは使い方も詳細に書いているので、その通りにやることをおすすめします。例文もタイピングしてピンインの復習もしていきます。
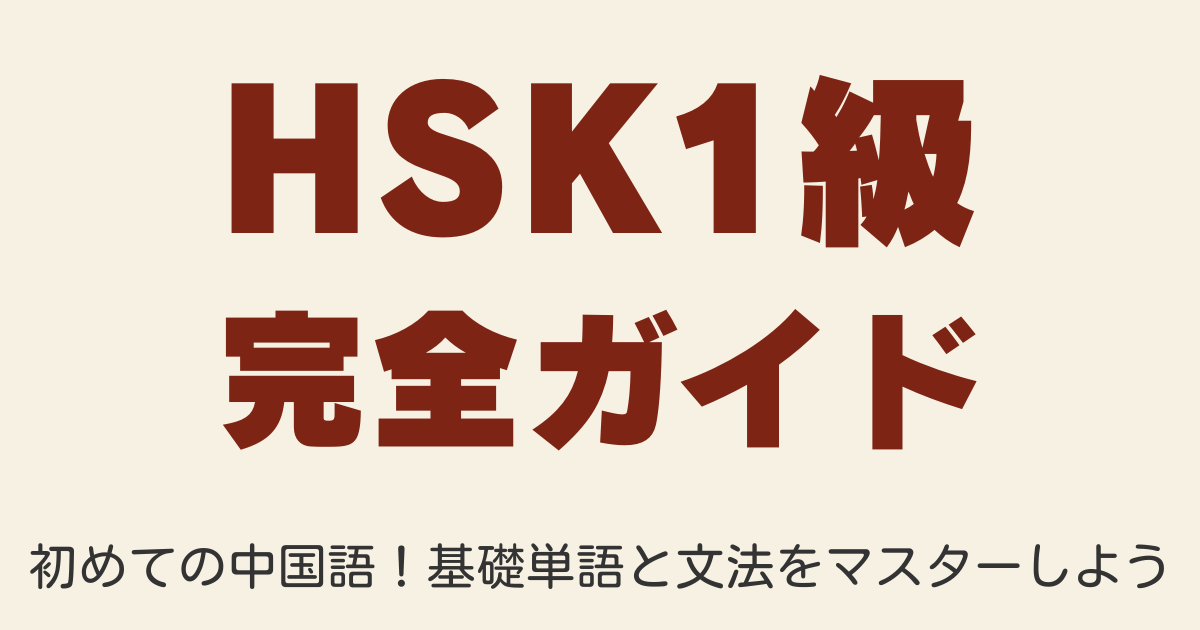
2.2 シャドーイング入門
シャドーイングは発音力とリスニング力を効率的に向上させる学習法です。文法レッスンの例文や会話文を繰り返し音読し、リズムやイントネーションを意識しながら練習しましょう。段階的にレベルが上がるように構成されているため、順番通りに繰り返し学習することが効果的です。まずは、シャドーイングの具体的なやり方を以下のガイドで確認し、基本をしっかり押さえましょう。
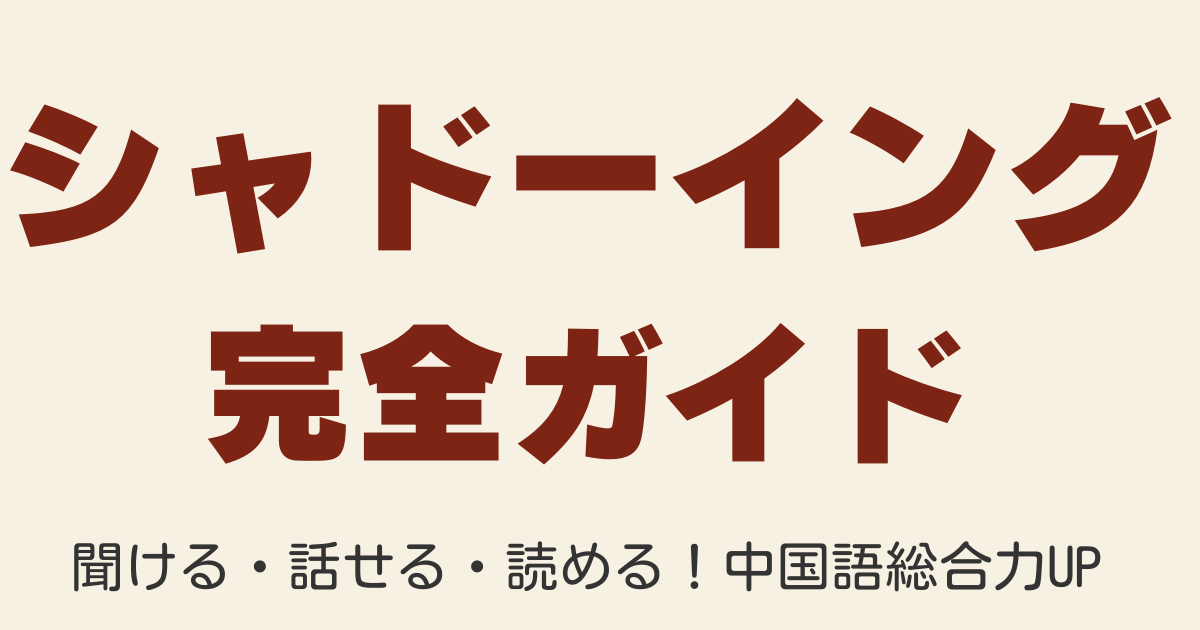
2.3 簡単なリスニング練習
入門段階から中国語の映画やドラマ、バラエティーを活用してリスニング力を鍛えましょう。ボク自身、ピンインを勉強しながら中国語の映画を観ていました。最初は意味がわからないことも多かったですが、意外と楽しめ、時には1日6時間以上観ることもありました。映画やドラマは、リスニングの練習に最適です。まずはリスニングの手順を以下の記事で確認し、効果的に練習を進めましょう。
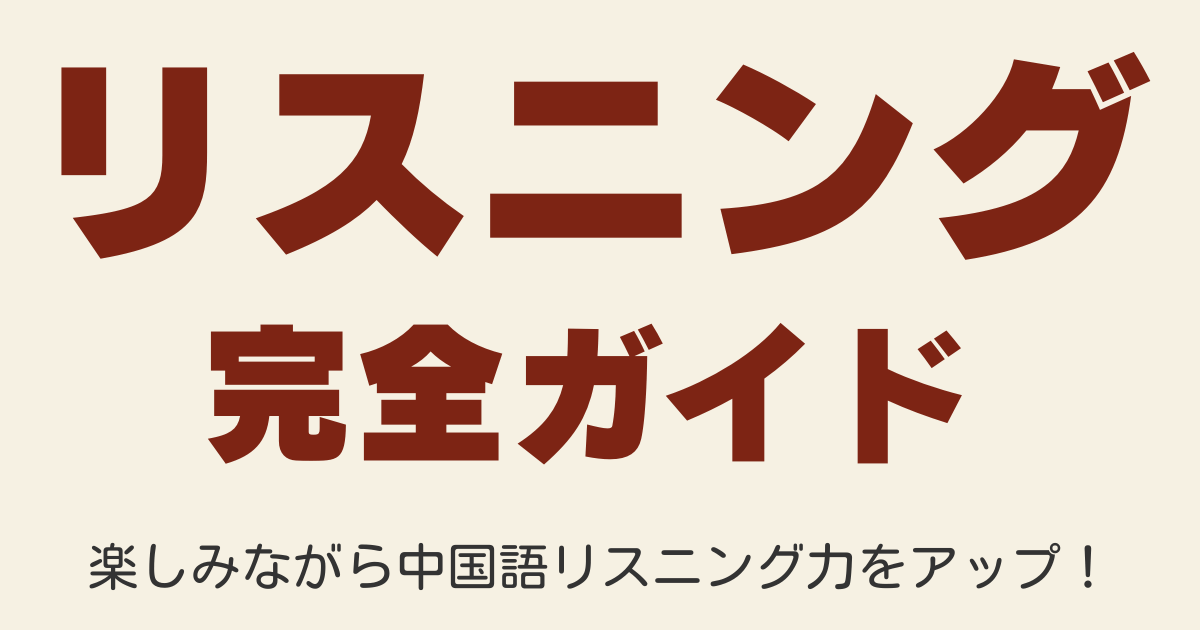
2.4 「カンニングしながら」のチャットや会話
学んだ語彙や文法を実際の会話で使うことが重要です。HelloTalk や Tandem などのアプリを活用すれば、世界中のネイティブスピーカーと簡単に会話練習ができます。これらのアプリでは、テキストメッセージ、音声メッセージ、ビデオ通話を通じて、実際の会話を体験できます。始めは簡単なフレーズや挨拶から始め、だんだんと複雑な会話に挑戦していきましょう。
勉強した例文をそのまま使ったり単語を入れ替えたり、いろいろ試行錯誤して脳を鍛えます。「私まだ入門レベルで何もできない。」と思うかもしれませんが、この段階が脳を鍛える黄金タイムです!恥ずかしい思いや失敗を積み重ねましょう。
また、CCレッスン や NOVA などのオンラインレッスンを受けるのも有効です。これらのレッスンでは、プロの講師とマンツーマンで練習でき、より実践的な指導が受けられます。特に、レッスンを定期的に受けることで、会話の流れを自然に学ぶことができます。
繰り返し練習を重ねることで、自然に中国語を使う感覚が身につきます。間違いを恐れず、学んだことを実際の会話で試すことで、効果的に語学力をアップさせましょう。
3. HSK2級 – 実践的な力を身につける
HSK2級では、基礎を固めた上で、実践的な力を身につけることを目指します。文法を応用しながら、リスニングやシャドーイングのレベルを上げましょう。さらに、チャットを使った実践練習を取り入れることで、実際のコミュニケーション力を高めていきます。次のステップへ進むための大切な段階です。
3.1 文法強化と応用練習
HSK2級では、基礎で学んだ文法を応用し、より複雑な表現やパターンに対応できるように練習を重ねます。この段階では、文法の理解を深めるだけでなく、それを実際の会話や文章でどう活用するかを意識することが重要です。
文法レッスンの使い方ガイドに沿って、シャドーイングを徹底し、その後音読で仕上げ、学んだ文章を卒業することが効果的です。この繰り返しにより、自然な語感と応用力を養えます。具体的な文法ポイントとその使い方については、以下の記事で詳しく解説します。
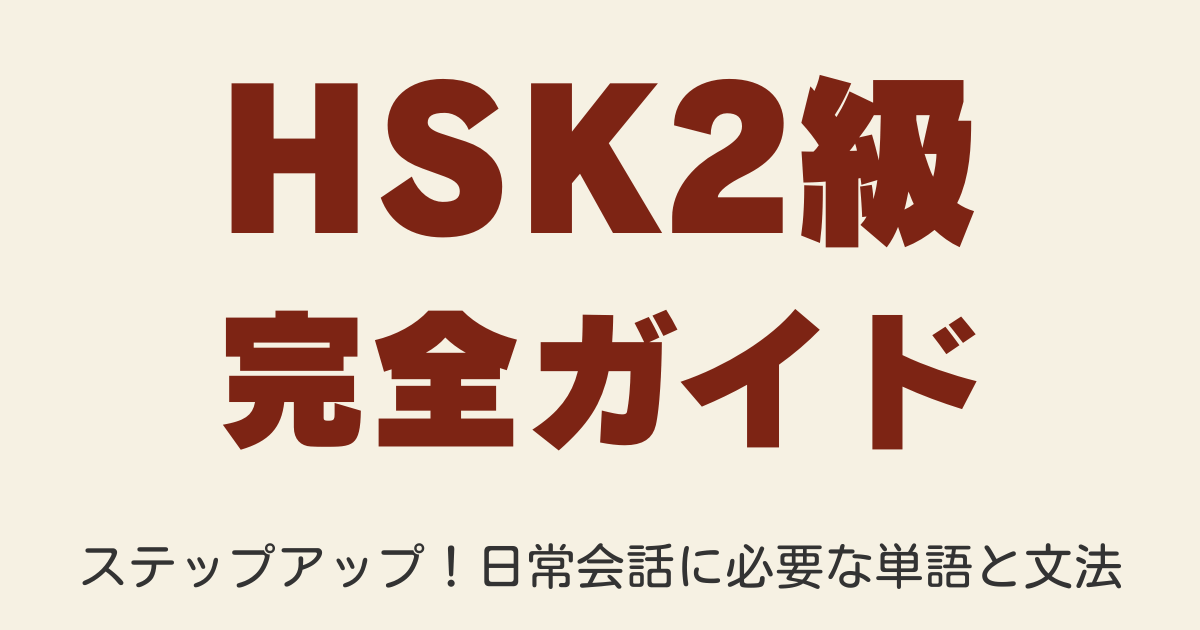
3.2 シャドーイング&音読
この段階でも引き続きシャドーイングを続けます。文法レッスンガイドで紹介した方法に従い、まずは音声に追いつけるようにシャドーイングを行い、その後音読に移ります。音読がスムーズにできるようになったら、次の文章に進みましょう。このプロセスを繰り返すことで、単語や文法が自然に頭に入ります。中国語脳を鍛えるためには、毎日の実践が欠かせません。
3.3 リスニングレベルアップ
映画やドラマ、YouTubeチャンネル、バラエティ番組、日常会話、ニュース、ポッドキャストなど、さまざまなコンテンツを活用して耳を慣らします。最初はスピードが速く感じることもありますが、繰り返し聞くことで理解できる範囲が広がります。時間があるときや休憩中に、できるだけ聴くように心がけましょう。
語彙力が増し、より複雑な文法や言い回しも自然に身につきます。毎日の積み重ねが、確実にリスニング力と読解力を向上させ、中国語脳を育成します。
3.4 チャットや会話の継続
前の段階でカンニングしながらチャットや会話をやってきましたね。この段階でも継続します。カンニングできる例文も多いので、それらをどんどん活用していきましょう。
勉強時間の中で、これらのアウトプット時間を増やすようにするのがいいです。最初は難しく感じるかもしれませんが、「実践しながら学ぶ」という姿勢で積極的に取り組むことが重要です。学んだ文法や単語をすぐに実際の会話で活かすことで、中国語脳を育て、より自然な表現ができるようになります。
4. HSK3級 – 中級へのステップ
HSK3級のレベルまで到達すれば、日常会話はスムーズにできるようになります。この段階で多読を取り入れます。
ボク自身、HSK2級程度で中国語を話せるようになり、その後は文法の勉強をやめ、しばらくアウトプットに集中しました。同時にシャドーイングや多読・多聴を続けていくと、中国語脳が育ち、語感が養われます。この状態になると、単語が頭の中で自己繁殖し、インプットで得られる情報が指数的に増えていきます。
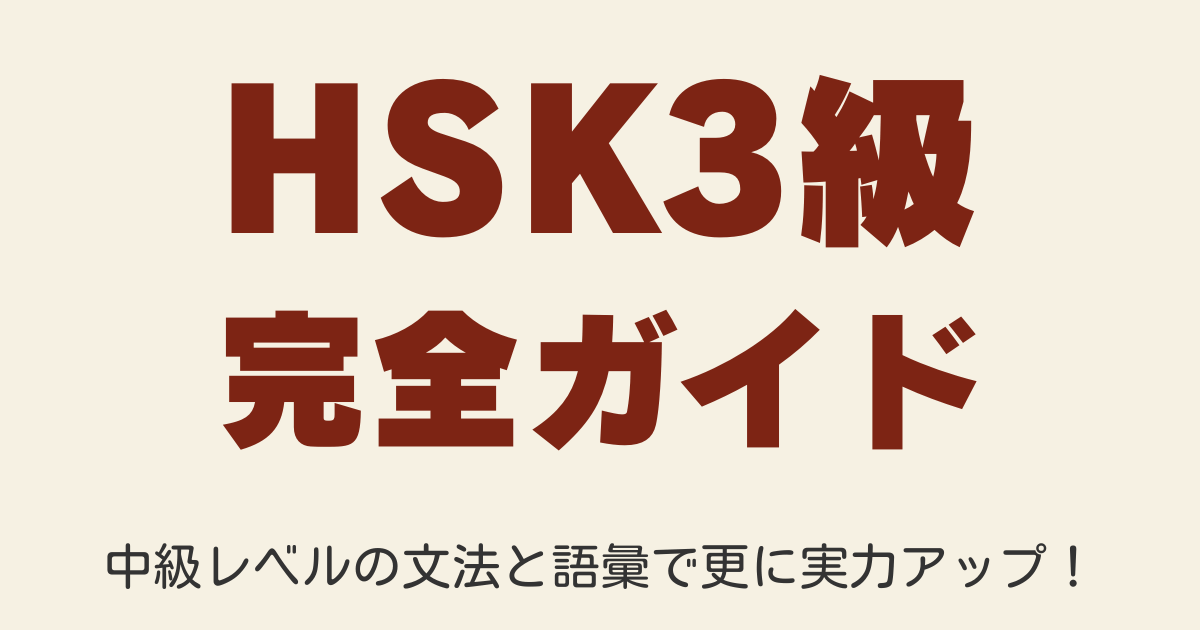
4.1 チャットやスピーキングの実践
HSK3級では、日常会話のスキルを強化し、実際の会話で応用力を高めます。現在学んでいるHSK3級の文法を積極的に使うだけでなく、HSK1級や2級で学んだ文法も意識的に取り入れましょう。文法レッスンサイトを辞書代わりにし、出てきた例文をアレンジして使っていきます。
また、語彙や表現が増えることで、さまざまなバリエーションを作れるようになり、カンニングしなくとも自分で文を作り出せるようになっていきます。多聴で学んだ表現も活用していきましょう。
実際にネイティブスピーカーとチャットや会話を繰り返し、リアルタイムでのやり取りを通じて反応速度や言葉の使い方を鍛えます。これにより、単に学んだフレーズを覚えるだけではなく、実践的な会話能力を身につけることができます。これには、HelloTalkやTandemなどのアプリを使った練習が非常に効果的です。さらに、音読やシャドーイングを織り交ぜて、言葉を自然に使えるようになるための反復練習を続けましょう。
4.2 多読の習慣づけ
多読は語彙力を増やし、文脈で意味を捉える力を養うために効果的です。この段階では、短い文章や絵本、子供向けの簡単な読み物から始めると良いでしょう。わからない単語が出てきても気にせず、量をこなすことが大切です。入門段階ではSNSなどの短い文章も活用し、わからない文章を「わからないまま」頭に入れることもものすごく重要です。詳しいやり方は以下の記事で解説します。
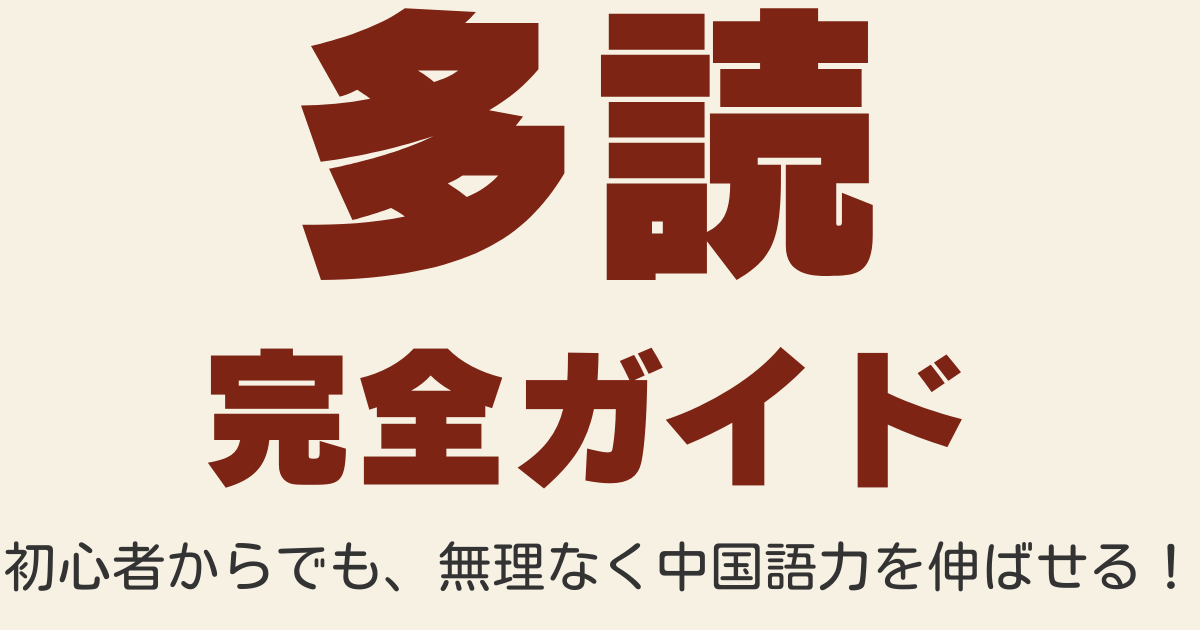
慣れてきたら速読を意識します。まず少し長めの文章を素早く通しで読み、文脈を大まかに把握します。単語やフレーズの意味を推測しながら、全体の流れを掴むことが大切です。詳細部分にこだわりすぎて読み進めるスピードが遅くならないように注意しましょう。その後、必要に応じて詳細を確認し、わからない単語や表現をチェックします。この方法で、短時間で多くの情報を処理する能力が身につきます。
簡単な記事や物語を繰り返し読むことで、語彙力が自然に増え、文脈から意味を推測する力も養われます。速読訓練を通じて、最初は理解よりもスピードを重視し、次第に精読を加えていきます。
4.3 実践的リスニング強化
この段階でも、意識して中国語を積極的に聞き取ることが大切です。映画やドラマを活用し、相槌の打ち方や日常表現など、細かい部分にも注目してみましょう。気になる表現があればメモし、チャットや会話で実際に使ってみると効果的です。
また、実際の会話の中で相手の話をしっかり聞き取る練習も欠かせません。中国語には地域ごとにさまざまなアクセントがあるため、アクセントの違いにも意識を向けて聞くことで、リスニング力がさらに向上します。
5. 実践と確認 – HSK4級以降の取り組み
HSK4級以降は、学習の取り組み方が大きく変わります。すぐに次のレベルに手を出すのではなく、まずHSK3級の表現を自在に使えるまで鍛えましょう。そのためには、多読多聴を一定期間繰り返すことが重要です。この段階で必要な中国語スキルはほぼ身についており、HSK4級〜6級の内容も自然とカバーできます。ボク自身も、文法学習なしでHSK6級に合格しました。
多読多聴が習慣化すれば、中国語学習は「卒業」と言っても良いでしょう。実践を通じて学び続ける最強ループが確立し、「中国語脳」が完成します。あとは、読む・聞く素材を徐々にレベルアップさせ、知的好奇心を満たしていけばOKです。
それでも気になる文法があれば、その時点でHSK4級以降の内容を確認すれば十分です。未知の文法があっても、それを使う機会は少ないでしょう。どうしても習得したい場合には、初期の段階と同様にシャドーイングや会話で実践していけば確実に身につきます。
この時期は中国語に触れる時間を最大化させた方が吸収が早いです。なので、日本語で本を読んだり、テレビを見たりする時間を削ってでも中国語に触れるようにしましょう。
まとめ
本記事では、HSK1級からHSK4級以降までの学習ロードマップを解説しました。学習初期では発音やピンインの基礎固めを重視し、徐々に文法、リスニング、多読といった実践力を鍛えていきます。リスニングとスピーキングを中心に訓練し、その後多読を取り入れるという流れです。ポイントは「学んでから実践」ではなく、「実践しながら学ぶ」ことです。
HSK3級までで日常会話力や速読力を習得し、HSK4級以降では多読多聴を習慣化して中国語脳を形成。文法は確認程度でOKとなり、使いこなす力が自然と身につくでしょう。
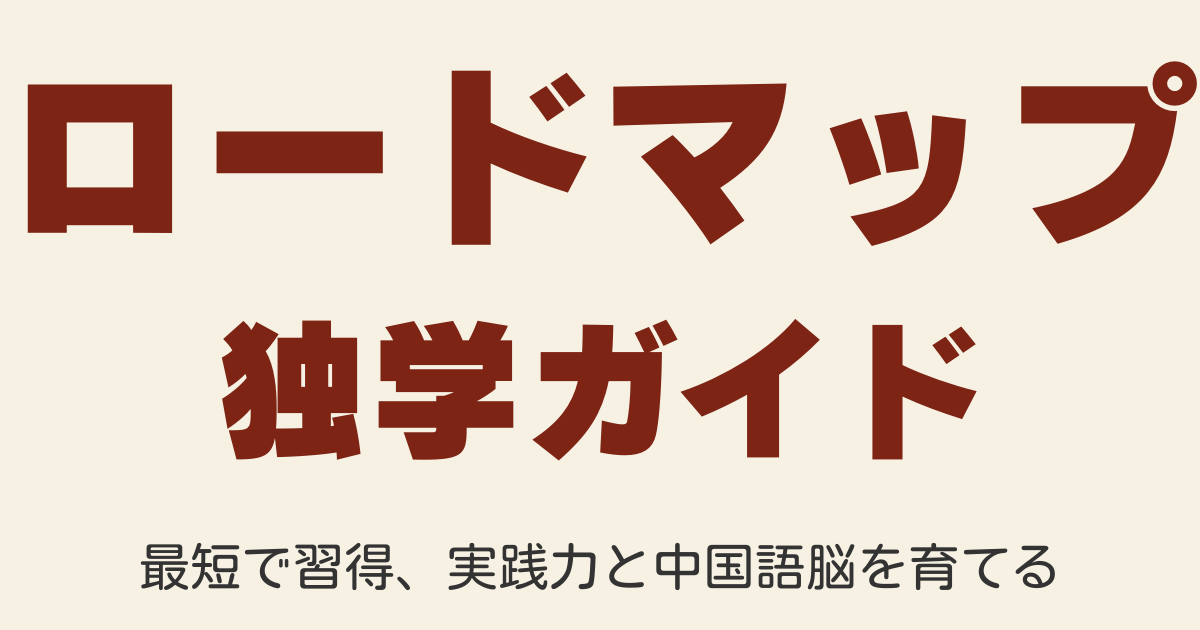
コメント一覧 (2件)
はじめまして、最前からyoutubeやブログなど楽しく拝見させていただいています。加藤と申します。自分は中国語学習者の大学生で高校時代に華人の友達がクラスに多かったため遊びがてら中国語を教わり、高一の際に(新)HSK5級で195点くらいでした。
一応同年スピーチコンテストで全国2位で、ネイティブにもまれていた為、南方訛りはあっても発音で日本人とバレる事は無かった(今もない)です。ただ、友達も中学からは日本なので、会話はお互い幼稚な語彙でした。
しかし、大学受験以降あまり話す相手もおらず、中国語からも離れていた為、語彙やリスニング力も減退し、ニュースや映画などにはついていけない耳になっています。
今でもHSK5級合格&リスニング9割ほどは取れると思います。
中国語のテレビを見て困らないレベルにしたいです。語彙不足なのか耳慣れしてない(離れた)のかわからないです。
何をしたらいいのかわからないので、もしよかったらアドバイスお願いしたいです。他に相談できる方がおらず、突然の質問で申し訳ありませんが、何とぞよろしくお願いします。
加藤様 メッセージありがとうございます!
初期のころからYouTubeやブログを見てくださってたのですね、感動です。
高校生活でクラスメートから遊びがてらに習ってHSK5級で200点ちかくの得点、さらに発音もネイティブ級ということはかなりのポテンシャルですね。
かなり語学のセンスがありますので自信をもっていいですよ。
スピーチコンテスト全国2位は相当な実力です。
知識や勉強習慣に関してはまったく問題ないことがわかりますね。
「語彙やリスニング力も減退し、ニュースや映画などにはついていけない耳になっています。」
とのことですが、受験の神様と呼ばれている和田秀樹によると
語学の能力はほぼ落ちないそうです。
記憶から取り出すのに時間がかかることはあっても脳の語感としては残っているらしいので、加藤さんの中国スキルは健在だと思います。
中国語のテレビを見て困らないレベルまでもっていくのは加藤さんの場合はカンタンでしょうね。
「耳慣れ」をつくることだと思います。
見たいジャンルのものを1日最低1時間じっくり見ていれば3ヶ月(100時間くらい)程度で満足できるレベルに持っていけるはずです。
もしくは1ヶ月でも大丈夫かもしれません。
語彙は中国語字幕で見ることで自然に増えます。
またできれば興味のある内容の文章記事を毎日読むようにすると語彙力UPも加速するはずです。
ボク自身の例を挙げると、動物が好きなので中国語の動物ドキュメンタリー番組を毎日見ていました。
3ヶ月くらいで、登場する動物や魚、昆虫の名前も自然に頭に入っていることに気が付きましたね。
さらに生息地の固有名詞も区別できるようになっていたのでドキュメンタリーを見ても内容がある程度わかる感じでした。
単語帳で単語を覚えたりはしていませんでした。
長くなってしまいました…すみません。
加藤さんみたいにポテンシャルがある方はあとは耳慣れだけで十分だと思います。
毎日1時間見るとして、最初の2週間から1ヶ月あたりで脳にある記憶の取り出しがスムーズになり、一気にラクになる感覚があるでしょう。
その後、2〜3ヶ月目の間で語彙もUPして満足できるレベルに達すると思います。
相談相手にボクを選んでくださったこと、すごくうれしいです!
また何かありましたらいつでもWelcomeですよ!
ありがとうございました。
ちゃいなサプリ
廣井佑樹