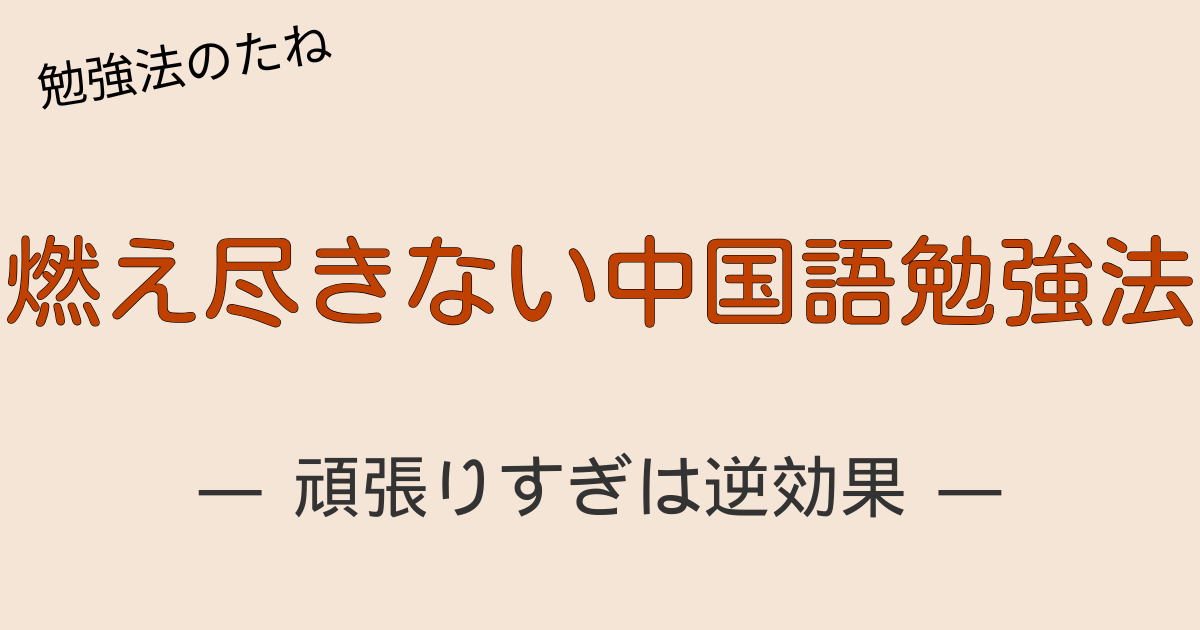中国語を学び始めたばかりの頃、誰しも「絶対にマスターしてやる!」と強い情熱を持ってスタートしますよね。
語学学習においてモチベーションは大切な原動力になりますが、
やる気がありすぎる状態がかえって逆効果になることもあるのです。
そんな学習の落とし穴について、ボクがYouTubeで解説した動画では、「儒教」や「仏教」の思想を参考に、中国語学習を無理なく・長く続けていくためのヒントをお話ししています。
本記事ではその内容をもとに、動画を見ていない方でもわかるように、ポイントを1500字ほどに凝縮してご紹介します。気になる方は、ぜひ動画と合わせてご覧ください。
「頑張りすぎ」がもたらす燃え尽き
中国語学習に限らず、最初は誰もがやる気に満ちています。1日10時間勉強するという人もいるでしょう。しかし、「燃え尽き症候群」という言葉もあります。一定期間、猛烈に頑張ったけど、急にやる気がなくなってしまうというものですね。
「こんなにやったのに全然上達しない」と感じて挫折してしまう人は少なくありません。勉強の効果がすぐに現れないと、極端に落ち込んでしまうのです。
大切なのは、「細く長く続けること」。情熱が冷めてしまったときでも、完全にやめてしまわず、ペースを落としてでも継続できるような学習習慣の構築が重要です。
以下の動画では、「人生100年も満たないのに、ひとは1000年あるかのように考える。」 中国語の情熱もずっと続いていくかのように考えて、途中で熱が冷めて挫折しちゃう例について解説しています。
中庸と中道の知恵:極端を避けるという考え方
儒教における「中庸(ちゅうよう)」
儒教における「中庸」とは、単に平均や中間を取るという意味ではなく、
両極端に走らず、時と場合に応じて適切な行動を取るという高度なバランス感覚のことを指します。
中国語学習に置き換えて言えば、「頑張りすぎ」も「サボりすぎ」も良くない。大切なのは、自分の体力・生活スタイル・モチベーションの波に応じた柔軟な調整力です。
仏教における「中道(ちゅうどう)」
仏教でも、「中道(中の道)」という考えがあります。これは、ブッダが悟りを開く過程でたどり着いた、苦行でも快楽でもない“極端に走らない生き方”です。
この思想は、語学学習にも非常に応用が利きます。ストイックにやりすぎても、怠けすぎても道は見えてこない。自分の心と体に正直に、無理のないやり方を模索することが大切です。
「好きすぎる」のも極端の一種?
「好きこそ物の上手なれ」という言葉がありますが、“好きすぎる”というのも一種の極端です。情熱的になりすぎて、「絶対に上達してみせる!」という強い欲望に支配されてしまうと、逆に苦しくなることもあります。
動画の中でも話したように、「ジャッキーチェンが好きだから広東語を猛勉強したけれど、興味が薄れたら続かなくなった」という経験があります。興味やモチベーションは“無常”であるということを意識することも、長期学習の鍵です。
学習のモチベーションは変化するもの
「今は中国語が大好きでも、その気持ちは変化していくかもしれない」。
そう考えておくと、学習の継続がずっと楽になります。
人の関心や情熱は常に変化します。今日は10時間集中できたけれど、明日は30分も厳しい。そんな日もあるのが普通です。
「毎日同じペースで、同じ情熱で頑張らなければならない」と考えると苦しくなります。変化に合わせて学び方を調整する柔軟性こそが、語学を長く続けるコツです。
詳細はnoteで深掘りしました。
▶︎続けられないあなたへ:“無常”で習慣を逆転させる勉強法
まとめ:大切なのは「細く長く続ける」姿勢
中国語学習において最も大切なのは、「極端を避ける」姿勢です。
- やる気があるのは素晴らしいことですが、燃え尽きないためにはペース配分が大事
- 中庸・中道の知恵は、極端に走らないための心構えを与えてくれる
- 好きという気持ちも変化する。だからこそ“習慣”として根付かせる
- 長く続けられる形を見つけることで、語学は確実に身につく
情熱を持って始めた学習も、それを“細く長く続けられる形”に変えていくことが、成功の鍵となります。今日の自分にとってちょうど良い学び方を探し、無理なく中国語と付き合っていきましょう。