こんにちは!ちゃいなサプリのYukiです。
中国ビジネス情報誌『销售与市场』第718期に紹介された記事から紹介します。
いま中国は「新消費時代」と呼ばれ、若者世代が新しい消費形態を作り出しています。
《新しい消費スタイル+新たな消費者+新しい生産方式》
で成り立っていると言われています。
これを理解するために最もわかりやすい例が果実酒なのです。
以下くわしく見ていきましょう。
新消費時代を理解する―「果実酒」
果実酒はすでに数百の新製品が出ていますが、そ
の後押しとなっているのがZ世代(1995〜2009年生まれ)なのです。
そのなかでもとりわけ女性が果実酒の消費の主力になっていることが注目されています。
お酒界の王:“白酒:bái jiǔ”は縮小へ
中国でお酒の業界で一番大きいのは“白酒:bái jiǔ”ですが、生産量は年々少なくなっていて、2016年に136億リットルの生産量に達してからは、その後急速に下降していきました。
2017年には12%下落し、2018年に27%、2019年に10%そして2020年には6%下落し、74億リットルにまで減少したのです。
2016年から2020年までの4年間で45.5%も生産規模が縮小したことになります。
「低アルコール+ほろ酔い体験」がブーム
アルコール度数の強い“白酒:bái jiǔ”(50度以上のものが多い)の主な消費者層は50代以上の年配層だとされています。

反対に若い消費者が好むのは「低アルコール+ほろ酔い体験」だといいます。
《年轻消费者带来的酒类消费革命:nián qīng xiāo fèi zhě dài lái de jiǔ lèi xiāo fèi gé mìng》という「若い消費者によるお酒類の消費革命」の報告によると、
若い消費者が主に好むのは「アルコール度数の低いお酒類」としています。
この年代の人たちはタピオカミルクティーやヨーグルトで育ってきているため、辛口のお酒は人気が出ないのです。
さらに若者の間では健康ブームもあり、お酒を飲むにしてもアルコールの低いものを選ぶようになっています。
健康ブームについてはこちらの記事もぜひ読んでみてくださいね!
【健康ブームの中国】「減塩」で「高顔面偏差値」ゲット!モテるために禁塩する若者たち
このようなこともありココ数年で果実酒の売上が大きく伸びています。
タオバオ(淘宝:táo bǎo )やTモール(天猫:tiān māo)などのECサイトでの売上の推移を見てみましょう。
2017年→2018年:154%UP
2018年→2019年: 45%UP
2020年→2021年:130%UP
低アルコールのお酒類での売上TOP3は
1位:RIO
2位:梅见:méi jiàn
3位:ほろ酔い
1位と2位は中国のブランドですね。1位は缶チューハイです。
日本では売っていないようなので、写真でご紹介しますね。


中国のドラマなどでよく登場しますので、見かけたことがある人もいるかもしれませんね。
2位は名前から想像がつくように梅酒ですね。
これは中国の江小白:jiāng xiǎo báiという白酒ブランドが出しているものですが、アルコール度数は12%です。
こちらは日本でも手に入りますので、ぜひ中国の若者トレンドを体験してみてください。
3位は日本のサントリーほろ酔いですね。
中国では日本のより少し割高になるので、ボクと妻は日本に帰ったときによく買っています。
中国にいるときには割高なので買おうとはおもわないですね…。
少女>子供>若い奥さん>お年寄り>犬>男性
現代の消費市場において、消費規模の大きい順に並べると次のようになります。
《少女>子供>若い奥さん>お年寄り>犬>男性》
男性はさいごに来ていますね。
今までは男性が主要な消費者であった「お酒類」は2021年にその主力消費者が女性に変わったのです。
2013年から90后:jiǔ líng hòu(1990年以降生まれ)の女性が店でお酒類を購入する割合が年々増加していき、2020年には男性の消費割合を上回りました。

2021年には果実酒やクラフトビールなどの市場において、若い女性が絶対的な主力消費者となったわけです。
今までは居酒屋やバーなどの飲み屋は商品やサービスで直接男性消費者を魅了してきましたが、今では優先的に女性消費者を呼び込み、男性はその「おまけ」のようになったのです。
新消費:秘密は「ちょっぴりやみつき」にさせること
新消費ブランドはSNSを主なマーケティング道具として、KOL(商品に詳しいインフルエンサー)や有名人をイメージキャラクターにして消費者にアピールします。
中国でよく使われるKOLマーケティングについてはこちらを参考にしてみてください。
【KOLマーケティング】中国ブランドのマーケティング手法を一挙公開
ではここで問題!
【問題】売上UPのキーポイントは以下のうちどれでしょう?
A.体験 B.需要に合っていること C.効率とコスパの良さ D.消費者がくせになること
若者の世代をじっくり観察してみるとコーヒーやタピオカミルクティーなどはおしゃれなライフスタイルには欠かせないもので、さらに低アルコール飲料などはほろ酔い気分という刺激を与えてくれます。
生活にサプライズが足りなければ、盲盒:máng hé(ブラインドボックス・カプセルトイなどチョコエッグ系の中身がわからないおもちゃ。ほかにはガチャポン類。)や福袋が中身がわからないドキドキ感を与えてくれます。

すなわち、若者たちはアルコールやコーヒー、お茶や砂糖などを摂取して身体の内部から精神的刺激を得て、その一方で、盲盒:máng héや福袋などでランダム性がもたらす心理的快感を得ているのです。
これらはすべて中毒性があり、一度その喜びを覚えるとくせになるというものです。
よって【正解】はD:消費者がくせになることとなるわけです。
果実酒がどうして新消費の主力商品になったのか?
女性ユーザーが多い中国版インスタグラムのようなSNS小红书:xiǎo hóng shū上での検索ボリュームを見てみましょう。
・果酒:guǒ jiǔ(果実酒) →8万以上
・女生酒:nǚ shēng jiǔ(女性向けアルコール)→10万以上
・微醺:wēi xūn(サントリーの「ほろ酔い」) →23万以上

2021年までにネット上の店舗、タオバオ(淘宝:táo bǎo )やTモール(天猫:tiān māo)で1507種類の果実酒が販売されていて、そのうちのTOP5が市場の45%を占めているのです。
さらに注目すべき点は、電子タバコのブランドの創始者やトップの人間たちがこぞって低アルコール飲料の業界にも足を踏み入れているということです。
タバコ・お酒というのはリピート率がかなり高いため、市場規模は巨大なのです。

果実酒ブームのきっかけ
果実酒がこのようにブームになったきっかけとして、海外から果実酒が輸入されたことにあります。
その火付け役となった果実酒を見てみましょう。
これらは日本でも売っていますから、楽天のリンクも貼っておきますね。
これを機に中国の若者トレンドに触れてみてください。

・フランスのシードル
これはフランスのブルターニュ地方発祥のりんごの発泡酒です。
ワインよりもアルコール度数は少なく辛口でも5%なので女性でも飲みやすいようです。
・ドイツベレンツェンのバーボンとリキュール
ドイツのベレンツェンという会社のアップルバーボンとライムストロベリーリキュールが中国では女性に人気です。
・日本の梅酒
中国でよく見かけるのはチョーヤの梅酒ですね。
これはローソンやスーパーなどにもおいてあります。
値段は日本より割高です。
ほかにはサントリーの梅酒もよく見かけるようになりました。こちらも日本の1.5倍〜2倍くらいの値段はしますね。居酒屋やバーなどではさらに高くなります。
・アメリカのフルーツワイン
アメリカのフルーツワインは甘口で女性にも人気です。
ワインはスーパーなどでも数多くの種類が並べられていますが、輸入品のものは日本のものより割高ですね。
日本では1,000円くらいで売られているものも、こちらでは2,000〜3,000円以上で売られていることもあります。
低アルコール飲料の今後の成長
このような低アルコール飲料は頻繁に買われるのではなく、場合によっては数ヶ月に1度買われる程度のものもあります。
このように購入頻度が少ないものはどのように100億元(1800億円)以上の市場規模に 成長できるのでしょうか?

筆者はそれは簡単だといいます。中国には650万のショップがあり、規模の小さいものやネット上の店舗もあわせればかなりの数にのぼります。
ライブ配信なども盛んに行われていますから、商品が消費者の目に触れる機会も増えてきました。
これから若者の消費が増えていって、果実酒がさらに注目されれば自然と規模は成長するのです。

若者たちは今では自己満足のために消費する傾向にあります。
以前は人からどう見られるかという「見栄」のための消費が盛んでしたが、今では人の目は考えず、自分が満足できるかということを重視しているのです。
このように中国のトレンドを左右するのは「若者」でしたね。
中国のこれからを予測したい人はまず若者を理解する必要があります。
次の記事も参考にしてみてくださいね。
今回の内容については以下の動画でも解説しているので、ぜひご覧ください^^
最後までありがとうございました!
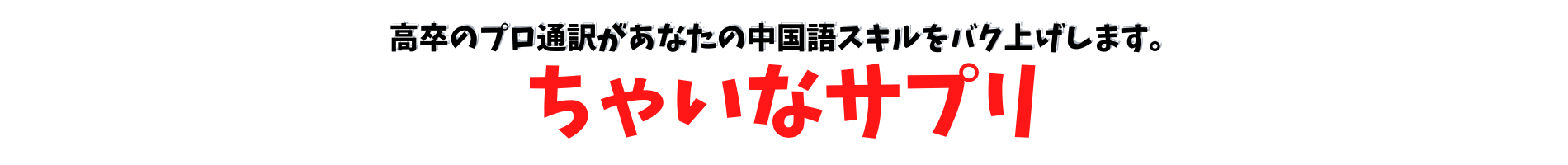



コメント